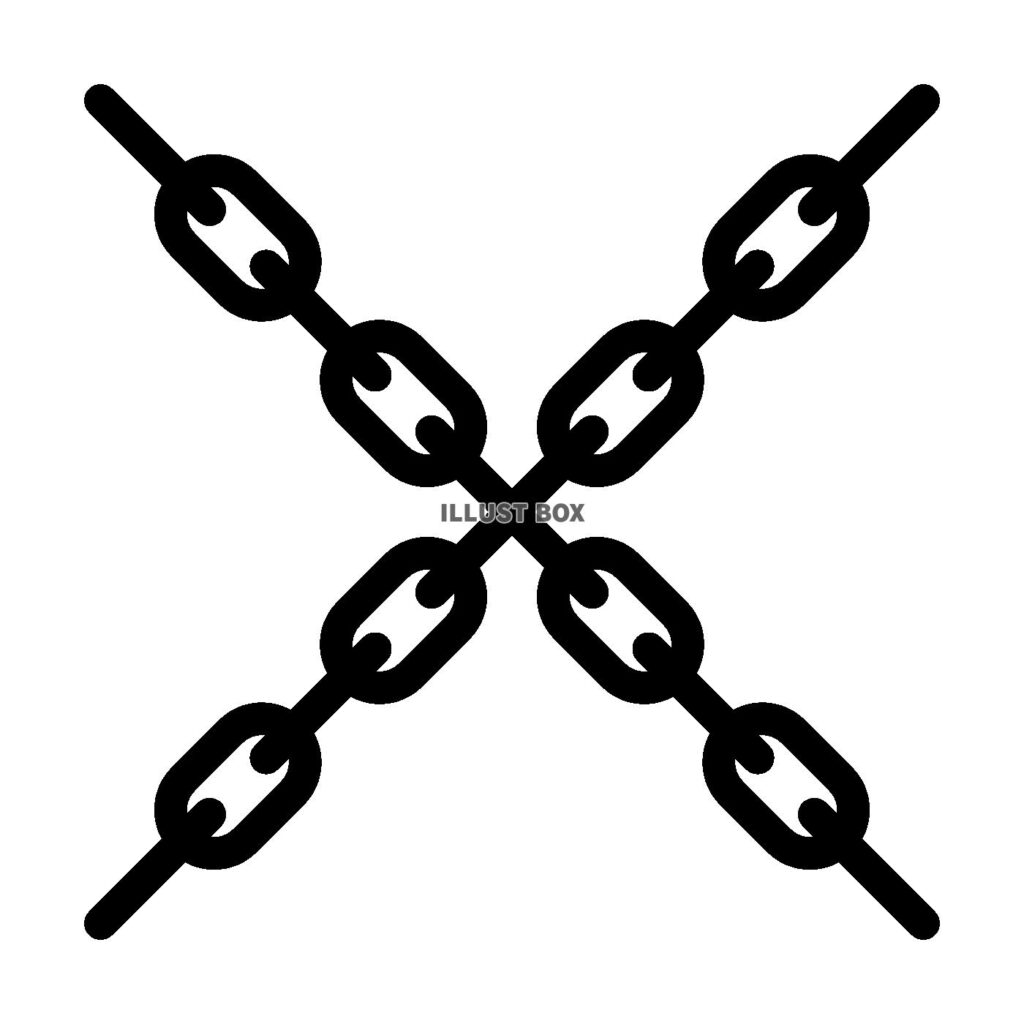
第三十六章 解放された漆黒の鎖 六話
「あ? 何言ってんだてめえ。つーか殺してくれる人間が目の前に居てくれてるのに、仮面なんて無粋なもん付けてんじゃねーぞコラ!」
握られていた手とは逆の左手で、おもむろに、仮面を剥ぎ取ろうとしてくるツエルブに対し、仮面の男は握っていたツエルブの手を放しバックステップで回避する。
仮面の男は何も動揺せず、ただ静かに、ツエルブをしとめる事だけを考え、片手にナイフを手にする。
奏根と順子は助かった事に安堵する暇もなく、ツエルブと仮面の男に注視していた。
奏根たちの窮地を救った仮面の男は一体何者なのか?
時は遡り、一時間前の十八時三十分。
網羅聖の銅羅のオフィスで深刻な話が飛び交っていた。
「それは本当か⁉」
「ああ」
明人は驚愕した面持ちで、ある秘密を銅羅から耳にする。
「何故だ⁉ 何故それを今まで黙っていた⁉」
明人は憤りを感じ、銅羅を問い詰める。
「君には私の仕事に専念してもらいたかった。仮に、君の姉が、ツエルブに襲われた被害者と耳にすれば、君は我を忘れ、ツエルブを殺しに行くだろう。そうなれば、共倒れになるか、下手をすれば警察に嗅ぎ付けられ、君は逮捕される。今まで正体がバレなかったのは、君に実力はあるが、それ以上に私たちの入念な下調べから導き出したプランがあったからだ。そうすればこの先、君のお姉さんは誰が守る? あの女狐が刺客として送り込む、人員は腐るほどいる。君もあの女の嗜虐性は理解しているはずだ。自分にとって用済みと判断すればツエルブを刺客として送り込む。クリプバに対して、あの女狐が唯一、関心を持っている理由は、莫大な金が手に入るからだ」
銅羅は珍しく落ち着かない様子を見せていた。
祥子の事を思うと、腸が煮えくり返る思いでもあり、同時に恐怖していた。
祥子こそ、網羅聖のトップ、サイレントアサシンと呼ばれる、殺戮マシーンなのだから。
「クリプバは裏で賭場としても扱われ、政治家たちには資金援助がされる。確かそうだったな?」
銅羅の焦りを伺った明人は、それ以上の詮索はせず、銅羅に話を合わせる事にした。
「ああ。あの女狐は利益になるかならないかで物事を秤にかけている。どこにでもいる疚しく醜く、下劣なハイエナだ。いずれ、君にあの女を抹殺して貰おうと、こちらでは検討しているつもりだ」
「なに⁉」
「君が驚くのも無理はない。それに反対したい気持ちも分かる。だが、このままあの女狐を野放しにすれば、砂川だけでなく、日本が未曾有の危機に晒される。果ては世界にも届くのだ、あの女狐の牙は」
銅羅は怒りと恐怖を押し殺しながら、明人に分かってもらおうと、懇切丁寧に、自分の胸の内を吐露する。
それを聞いた明人は、俯き、思案する。
それが正解なのか? と。
「だが今すぐにとは言わないし強制ではない。それに私は君の意思を尊重する。これについては今は忘れてくれ。それよりも今はこれだ」
銅羅は冷静を装いながら、一枚の書類を明人に見せる。
提出された書類に目を通す明人は、眉を顰める。
「またか? ツエルブの奴、今度は、アサルトハイドチームに敗れ、クリプバを引退した選手の抹殺?」
「その下にある文章も読んでくれ」
銅羅はかなり動揺している様子だった。
あれだけ、大胆不敵で貫禄ある立ち振る舞いをしていた銅羅が、やけに焦燥している様子を目にした明人は、一体何が書いてあるのか、覚悟を決めて目を通す。
「……ダイオンジチームの監督、洲上達樹の抹殺指令……」
注意深い目で口にする明人は、どこかげんなりする様子を見せていた。
どれだけ、人を殺したがるんだ、奴は、と心の内で思いながら、内心穏やかな様子を見せていない明人。
それに対し、銅羅は、テーブルに両肘を付き、両手で顔を覆い隠す。
「その達樹さんと言う人は、私の恩師の様な人だ。私が子供の頃、経済の知識や事業を起こす仕組みなど、教授してくれた。それだけでなく、人としての定義について、談笑しながら語り合っていた。恩師でもあり、私の旧友なのだ」
珍しく、人を尊敬する様な仄めかす様に言う銅羅に、明人は「そんな恩師が居て、お前はこのざまか? さすがは自称社長と言うだけはあるな」と嫌味を口にする。
「それについては反論できない。私は私で行く指針を決めてしまった。もうあの人に合わせる顔は無い。だが、あの人がこの世から居なくなるのは避けたい。頼むスフィア。これは仕事ではない、私個人としての頼みだ。どうか達樹さんを救ってくれ」
嫌味を反論する元気もない達樹は、小心したかの様に、これまた珍しく飼い犬として扱っていた明人に懇願する。
図々しい願いではあるが、明人も人の子。
明人からしてみれば、忖度なしで、無償で助けるにはこれ以上の理由は無かった。
「……分かった。今から行けばいいのか?」
「そうだ。達樹さんは珈琲店の喫茶店で、脅迫者と会う約束になっている。恐らくそこか別の所にでも誘き寄せられて殺されるはずだ。頼む」
明人は秘密裏に動いていた銅羅を咎める事無く、不愛想な面持ちではあるが、この時、初めて銅羅に優しさを見せた。
顔や雰囲気には出さずとも、その気持ちは銅羅にも伝わっていた。
「これを付けて行くと言い。少しは警察の目からは逃れられるはずだ」
「分かった」
そう言って、般若のお面を渡す銅羅。
そして、明人は静かに、敏捷に、動き始めた。
もう間に合わなかったとも知らずに。
そして今に至る。


コメント